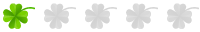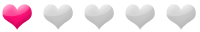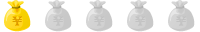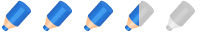なんとか、息をしている。
いや、ホント、よく乗り切れたものだ。
今年に入って、新たな仕事に就いたことは以前記事にも書いたとおりだが、不慣れな仕事に四苦八苦している最中、数年に1回あるかないかの“ややこしいお仕事”が半月の間に3つもバッティングしたのだ!
人間、パニくると、突然、思考停止になることがある。PCでいうところの、メモリー容量不足でフリーズするようなものだ(笑)小生も、この半月、PCに向かいながら「今、何をするところだったのか・・・」と気絶することが何度かあった(爆)
メンタルの強さには少々自信があったが、流石に今回は飯も喉を通らず、毎日、胃薬を飲みながら過ごした(笑)
まぁ、なんとか一部は収束したので、久々の更新である。
とはいっても、今回は手抜き!(爆)次回の記事ネタにつながらる“ネタ”のコピペである。
それは何か・・・これまでの、おさらいの意味をこめて、、、かつて愛用してきた、そして、今も愛用しているクレル製品の数々を、仙人郷での写真を交えながら、クレルの軌跡をふりかえろう。
////////////////
1979年創立。
1980年1月、処女作KSA-100をラスベガスのウインターCEショーに出品してデビューを飾りました。
そのステレオ・パワーアンプは、手加工ならではの味わいをもったシルキーホワイトのアルマイト仕上げパネルに金メッキ仕立ての止めビスを配するという、それまでにない瀟洒なデザインと、そして、緻密な再現性とエネルギー感を両立させた自然で温かい肌合いをもつ音で、瞬く間に世界のオーディオファイルの心をとらえました。
創立者、そして設計者であるダニエル(ダン)・ダゴスティーノ氏は大学時代に電子工学を専攻、その後海軍で高周波関連に従事。除隊してからはフリーのエンジニアとしてオーディオのアンプからスピーカーまでの設計、測定、クリニックまでの仕事に携わり、70年からはカナダのデイトンライト社で主導的な立場でエレクトロ・スタティック・スピーカーの開発に関わったり、スレッショルド社でエレクトロニクスに携わります。
75年からはイギリスのゲイル社、77年からグレート・ホワイト・ホエール社でアンプの開発を担当した後、独立します。そして十数ヵ月の間、ピュアA級アンプの研究開発に没頭。79年秋に最初の製品試作機が完成し、コネチカットの工場でクレル社の第一歩がスタート。33歳の年でした。
ダゴスティーノ氏夫人のロンディーとたった二人で完成品を組み上げ翌年の1月のCESにはるばる持ち込んだ記念すべき第一号機、ピュアA級パワーアンプKSA-100はまさに大センセーションを巻き起こしたのでした。
オーディオブランドとしては一風変わった<KRELL=クレル>というネーミングは、彼が以前から温めていたもので、少年時代に観て感動したSF映画の傑作「禁断の惑星」(1956年・アメリカ)に登場する惑星の偉大な先住者の名「クレル」に由来します。「クレル」は惑星の地下にほぼ無限のエネルギーを蓄え、高度な文明を築き上げていた。・・・と言う物語に、のちにオーディオの仕事に就きアンプ設計者として苦労を重ねて興した自分の会社と設計するアンプのコンセプトへのイメージをダブらせました。それは揺るぎないエネルギーを生み出す強大な電源をもつ品位の高いA級ハイパワー機の創造だったのです。完成した自らのアンプをまえにして彼は、映画を思い出しながら<クレル>と名付けたのでした。
KSA-100は純A級で100W+100Wの出力を有し、あらゆる出力状態での完全なA級動作を誇りました。
負荷インピーダンス対出力特性のリニアリティーの良さは抜群で、2Ω負荷で380Wを保証するというパワー能力は当時に於いて驚異的。また、電源トランスから独立した完全デュアルモノ・コンストラクション、スペースを十分にとったレイアウト、パワーTRを常時70°Cに保つためのローノイズファン・クーラーの採用、そして厳選したパーツを使用したシンプルなピュア・コンプリメンタリー回路など、粋を凝らした設計でオーディオファイルを魅了しました。
●デビューに続くクレル第一世代
KSA-100に次いで発表されたのは、独立した電源でボリウムまで別々の完全デュアルモノのプリアンプPAM-2。極力単純化したシグナルパス、ハイグレード部品でかためた最高水準のS/Nを誇る高級機です。
ハイエンドのオーディオァイルのみを対象に絞った超高級アイテム・クレルのラインナップがいよいよ始動します。
1986年までの数年間、パワーアンプではKSA-100をベースにしたバリエーションモデルを展開。同一構成で50W+50WのKSA-50、さらには、モノラルタイプのKMA-100,200及びそれぞれのMK2バージョンです。「KMA」タイプは「KSA」の内容をパラレルにして、2Ω負荷でもまさに完璧な安定したパワーリニアリティーを実現しています。
KSAに比べて、全体に音の立上がりがよりシャープになり低域もさらに締まってエネルギー感が加わり、しかもローレベルでの敏感な反応ぶりで当代最高のクオリティーを備えたパワーアンプの一つと讚えられ、<クレル>ブランドを不動のものとしました。
プリではPAM-2に次いで81年に発表したKRS-1(クレル・リファレンス・スタンダード)で一つの頂点を目指します。完全モノーラルで、アルミ・ブロック削り出しのシャーシーを採用するなど贅を尽くした別電源4ボディー構成のプリアンプは、まさに考え得る限りの最高を極めたと言っても過言ではないでしょう。
数年後のPAM-3は、こうしたモノーラル機の性能を一つのボリウムコントロールで操作できるステレオ機に於いて追及した意欲作です。いずれもその洗練されたデザインとともに、質感の高い音を評価されています。
●クレル第二世代
1987年にはいってからのパワーアンプに於ける一大テーマは冷却用ファンの追放でした。いくら静かなファンを使用していたといっても皆無ではありません。リスニング環境のより高いS/Nを実現するためにファンを排除して自然空冷のシステムを全面的に採用することに着手します。
妥協を排し、全てを一から堅実に見直します。結果、2Ω負荷800Wまでをリニアにクリアするためのヒートシンクや電源はとてつもなく巨大化。 それはモノーラルアンプKRS-200として結実し、「超弩級」の名を欲しいままにします。
丁度、アポジーなどの平板型スピーカーがアメリカで主流になりつつあった時期に符合するように低負荷駆動能力を求めてヘビーデューティーになり、それまでのクレル・トーンから、徐々にエネルギッシュで華麗なキャラクターへと変貌します。
しかしその一方で、反動とも言える実用サイズのKSA-200(これは100W以下でA級、それ以上AB級動作)やさらに小型のKSA-80やALTAIR(AB級)などもラインナップも加えられ、幅を拡げます。
●クレル第三世代
1990年、オート・キャリブレーティングによるA級動作に於けるバイアス切り替えの技術を確立。
実用的なサイズで発熱をセーブ・適正化する自然空冷のA級アンプとしてクレルの現在に至るまでの基幹モデルとなったKSA250では、伸びやかでハツラツとし、安定した力感、音像定位の良さで新しいクレルの魅力を出してきます。
後のMDA-500などのモノラル機ではKSA-250のパラレル化で入力から出力まで初の全段完全バランス構成を達成。出力トランジスターの数は実に48個。因みにMDAとはモノ・ディファレンシャル・アンプリファイアーの頭文字です。
ここまでの間、クレルは比較的短いサイクルで意欲的に新製品を送り出しています。技術的進展に伴った必然のステップアップではあったのですが、それは裏腹に市場での若干の戸惑いを招いた事も一方に於いてまた事実でした。
二世代目、三世代目とゆくに従って、いかにもアメリカのアンプらしく熱っぽく力に溢れた音となり、それなりに魅力的ではあるが、逆に初期のクレルの音の緻密で洒落た味わいが稀薄になってしまった。と言うような批評もあり、一方で反動的な製品とも言えるAB級機のKST-100がそれに対応するプリKSLとともに、逆に新しいクレルの音をもたらしたとして、その空間に浮き立つようなさわやかで暖かな音を高く評価されたこともある、半ば皮肉な時期でもあったと言えるかも知れません。
この頃、一方ではKC-100,200などのMCカードリッジやKPAフォノEQをもリリースし、KSP-7やKBLなどの一連のプリアンプとともにアナログの入り口を増強しています。
また、1991年発表の高S/N・完全バランス・アクティブクロスオーバー・KBXは若干姿を変えながらも現在まで尚継続されている隠れたロングセラー機です。様々なブランドの様々なモデルのスピーカーに対して、メーカーのソフトウェアに合わせて製作された個別対応のプラグインカードを使用し、最適なクロスオーバー周波数、スロープ、イコライゼーションが正確に得られる優れたシステムです。
●クレル第四世代
少しのインターバルをへて1992年、新シリーズに移行。
KRC,KRC-2など、リモコン対応の高精度アッテネーターを搭載したプリの登場ととともに、新技術によるパワーアンプは覚醒の時期を迎えます。
バイアス切り替えの技術を更に押し進めたSPB(サスティーンド・プラトー・バイアス)というパワーに応じて5段階にバイアスを切り替えるスライディング・バイアス回路と、1800V/usのスピードで出力段の動作よりも18倍も早く入力信号を検出することで、音楽信号を全く損なわずにSPBをコントロールするアンティシペーターという予測センサー回路、そして、出力トランジスターと同数のトランジスターよる出力段電源・完全レギュレーターの搭載など、技術の集大成を盛り込んだモノラル機の新たなフラッグシップ・モデルとしてクレル・オーディオ・スタンダードKASと姉妹機のKAS2をリリース。
出力トランジスター、レギュレーター・トランジスターの数は各々KASが60個、KAS2が20個。ドライブ能力は1Ω負荷でKASは何と3040W、KAS2でも1400Wに達し、0.1Ω負荷でも安定した動作を保証すると言うもの凄さです。大型機とは思えないしなやかな表情となめらかな抑揚、底力のある深い低音の鳴りっぷりはまさに熟成の薫りと高い評価をうけています。
また、そのコンセプトを大幅に取り込んだステレオバージョンのKSA-300Sなどの穏やかなデザインのSシリーズ・パワーアンプも3機種を揃えてラインアップを拡充させます。
電源の配慮については特筆されます。 クレルの電源トランスはチェロ、マドリガルなどハイエンドメーカーの多くが採用している英国ホールデン・フィッシャー製のトロイダルトランスを徹底した選別で使用。また、特にSシリーズの電源トランスなどは、僅かな振動も許されない潜水艦で使うトランスを作るメーカーのものが採用されています。
もう一つ、クレルの特徴として上げられるのは、いちはやく取り組んだきめのこまかいアップグレード・サービス体制でしょう。マイナーチェンジ・バージョンやマーク2バージョンへのモデル展開に際しては、必ずベーシックモデルからの同一機能へのアップグレード・サービスを行なってきました。ユーザーに常にその時の最新性能の提供を約束する姿勢は、創業以来一貫して変わっていません。
プリアンプの最新作は1995年リリースのKRC-HR,KRC-3の二機種があります。KRC-HRはKRCをベースに、アッテネーターをディスクリート構成によるR2Rとし、オプチカルエンコーダーで動かすトップモデル。また、KRC-3は同様のR2Rアッテネーターに加えて、クレルとしては初めてのカレントモード・デザインを採用する高品位モデルです。
●クレル第五世代
1996年春、初のインテグレーテッド・アンプK-300i(KAV-300i)、そしてSシリーズを全面的にリファインした最新ステレオパワーアンプFPB(Full Power Balanced) 200、300、600の三機種を発表しました。
K-300iはクレルがKASをはじめとするパワーアンプで使っているものと同じカスタムメイドのモトローラ・バイポーラ出力素子を採用する150W/chのパワーステージと、全段アクティブ・ディスクリートのコンプリメンタリA級増幅のプリステージを持つ極めてCPの高いインテグレーテッドです。
また、クレルの新しい顔FPBシリーズは超高速でリニアな増幅を行なうカレント・モード・ゲインステージを採用し、SPB(サスティーンド・プラトー・バイアス)をより有機的に機能させる新SPB-IIを導入。
入力から出力に至る全段完全バランス構成による洗練されたサーキットと、そして、風格の漂うシンプルなコスメティック・デザインは、新たなる<クレル>伝説の始まりを予感させました。
1997年、FPBシリーズをモノーラル化した250、350、650をリリース。
同年、それまでサブ組織として1989年からDACやCDを主体としたデジタル関連製品を開発してきたKrell Digital Inc.を統合。SBP-64X、REFERENCE64などの優れたDACや、MD-1、CD-DSP、KPS-20iなどいまだに愛用者が多く独特の味をもつCDプレーヤー開発の実績を基に再スタートを切ります。
KAV-300cdを手始めとして、翌年の最高級システムKPS25sに続き、KAV-250cdやCAST電流出力をもつ画期的なCDプレーヤーKPS28cなどを相次いで開発。クレル総体としての新たな展開を促しています。
また一方、1998年にかけては、KAV-250a,KAV-500などのパワーアンプ、サラウンドプロセッサーA+V Standard、インテグレーテッドアンプKAV-500i、3チャンネルパワーアンプKAV-250a/3などを相次いで発表し、“HEAT”ハイエンド・ホーム・オーディオ・シアターのコンセプトを積極的に推進しています。
●CAST技術
1998年、100有余年に及ぶアナログオーディオの歴史を揺さ振る程の一大革命とも言える“CAST”テクノロジーが出現しました。アナログ伝送の形態として唯一無二であったこれまでの電圧信号伝送に代わって、CASTでは電流信号を伝達します。伝送ロス比を数十万分の一に抑えることのできる全く新しいクレル独自のこの方式は、ダン・ダゴスティーノが思いのままに製作する、新しいトップエンド・シリーズ“マスター・リファレンス”の第一作目となる巨大なパワーアンプ“MRA”と、追って発売されたCDプレイバックシステムKPS25scに装備され、無限の可能性を示唆しました。
1999年に入り、そのCASTはFPBシリーズの全てのパワーアンプに搭載され、それらはFPB”c”シリーズとして生まれ変わっています。(200c,300c,600c,250Mc,350Mc,650Mc) HEATシリーズでは新モデルHome Theater Standard を発売。より幅のひろい対応力をアピールしています。
2000年、マスターリファレンスシリーズに究極のサブウーファーMRAが登場。CASTもいよいよ本格化し、FPB”c”シリーズに対応する夢の電流伝送プリアンプKCTとDACの電流出力をダイレクトに電流増幅し出力させるKPS28cが完成。その圧倒的なポテンシャルによって構築される未来的なシステム展開に至るCAST第二ステージの幕が切っておとされたのです。
●クレル第六世代
2000年、スピーカーエンジニアとしても、屈指のノウハウを持つダン・ダゴスティーノがクレルブランド初のスピーカーLAT-1を開発、センセーションを起こします。2001年、KAV-300はiLバージョンとなり、スピーカー第二弾LAT-2とマルチチャンネルパワーアンプ、TAS,KAV-2250,3250そして、初のマルチディスクプレーヤーDVDStandardなどを立て続けにリリースし本格的なホームシアターアイテムの訴求に勤めます。2003年、高音質サラウンドプロセッサー/アンプのShowcaseシリーズと同時に、初のSACD/CDプレーヤーSACD Standardを開発。KAV-300iLはKAV-400xiとなり、圧倒的な支持を集めています。
2005年、LAT-1のアップグレードモデルLAT-1000と、ピュアオーディオの真髄を極めるステイタスモデル
Evolution One/Twoを発表。2006年、Evolutionのテクノロジーを従来のFPBシリーズに波及させる新たなプリ 202,222、パワー402,600,900、デジタルディスクプレーヤー505など一群のEvolutionシリーズを発表。2007年には往年のクレルを彷彿とさせ尚その先をゆく音とC/Pを誇るシリーズ完結モデル”Evolution302″ステレオパワーアンプをリリース。クレルのオーディオマインドとスピリッツが再び大きく開花しています。
●クレル新世代
Evolutionシリーズ発表後、クレルは創立者、D・ダゴスティーノ氏の離脱という大きな転換期に直面します。しかしKAS開発時よりクレル設計開発は、同氏をリーダーとするR&Dチームとして活動して来ました。
多くの独自技術の開発は設計チームでの作業となり、多くの技術者により達成される集大成とも言えるでしょう。
デイヴ グッドマン氏(Dave Goodman)を新たな設計リーダーとする開発チームは、超高速スイッチング機能「インテリジェントHDMI」を携えた新世代AVプロセッサ「Foundation」を2013年CESにて発表します。
ダゴスティーノ氏が推進していた中国での生産を一切中止し、全て本社による生産に移行したのもこの年です。
●iBias Class A テクノロジー
2014年、グッドマン氏は長年の沈黙を打ち破る新たなClass Aアンプ、iBiasシリーズを開発します。ClassAアンプが抱える「発熱」と「大消費電力」の問題に正面から取り組み、この問題を打破する新技術が”iBiasテクノロジーです。
従来の入力信号波形によるバイアス設定では、繋がれるスピーカーの仕様に拘わらずその電流量は決定されてしまう問題を根底から見直し、出力側の消費電流をもモニタリングする事で如何なるスピーカーに対しても最適なバイアス料を設定します。
また効率を上げ、生産コストを抑える事も大きなテーマとなりました。
iBiasシリーズではステレオ、モノラルにそれぞれ2機種のモデルが用意されています。その全てのモデルに使用される躯体は同一とし、またモジュール化されたパワーブロックは組み合わせる数によって出力を決定します。多くのパーツを共有化する事で、高いクォリティ維持と生産コスト低減を達成したのです。
また全て米国クレル本社での生産となるマルチ・チャンネルアンプへもこのパーツを投入。最大7チャンネルまで用意されたマルチ・チャンネルアンプも、全てClass Aアンプへと生まれ変わります。
クレル社の血統を受け継いだデイブ グッドマン氏による新たな製品群は、新世代クレルへの扉を開けたのです。
////////////////
というわけで、クレルのお勉強はこれで終わり(笑)
次回は、当然、クレルつながりのネタということで・・・・・次回をお楽しみに!(いつになるのやら・・・(汗))